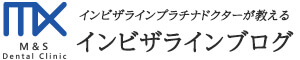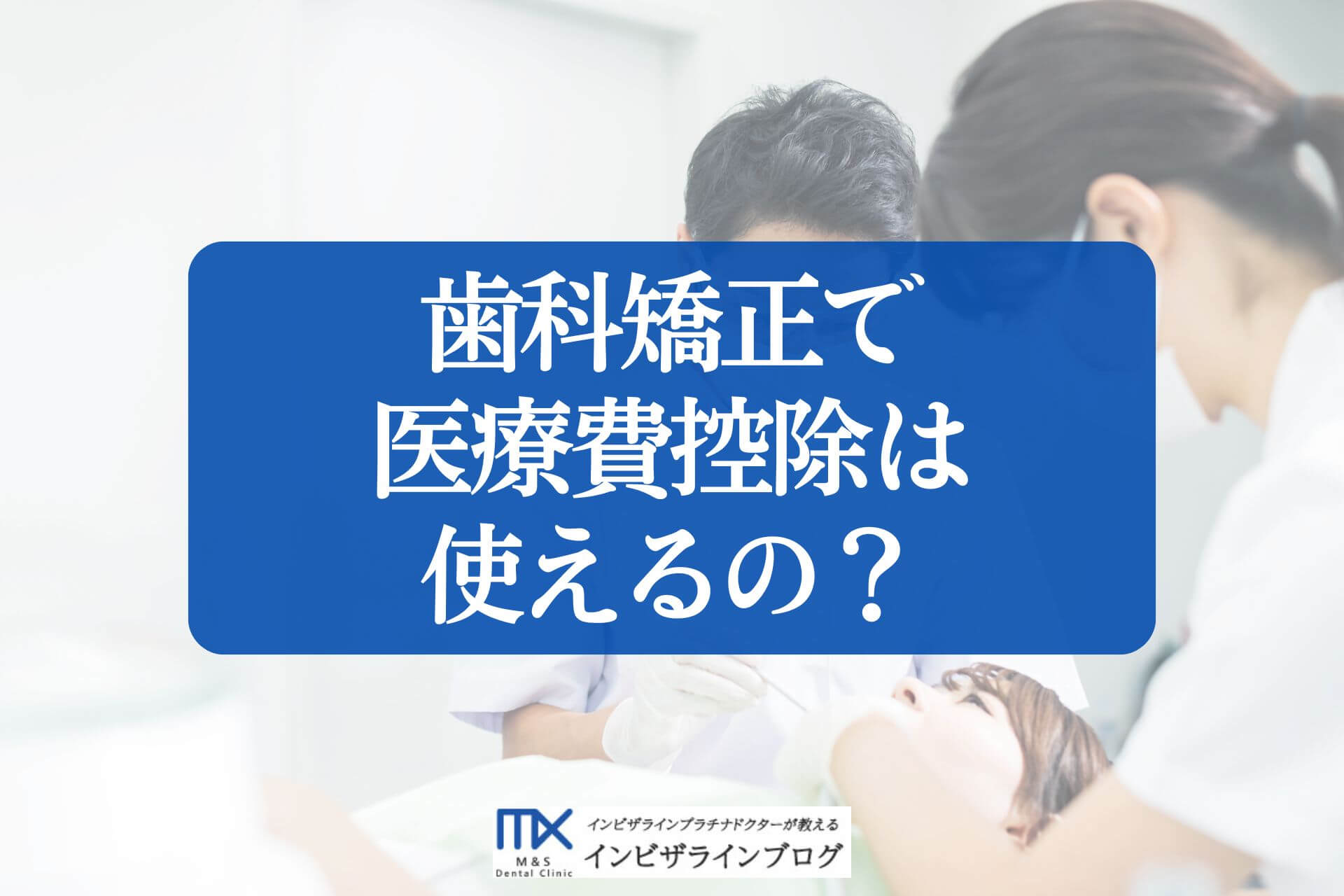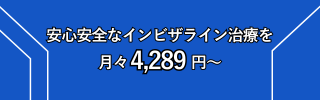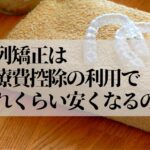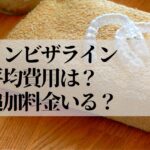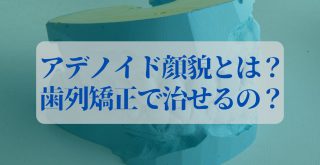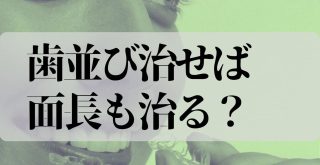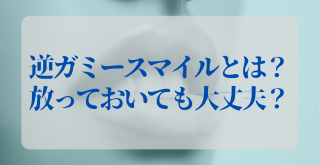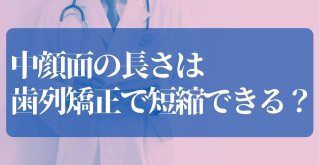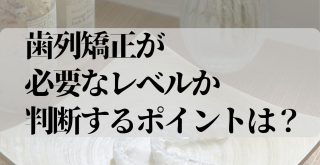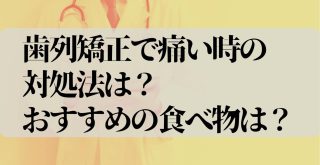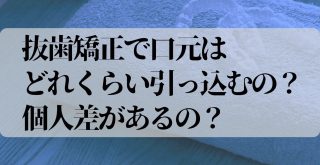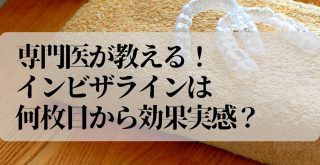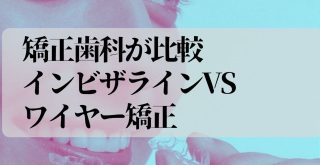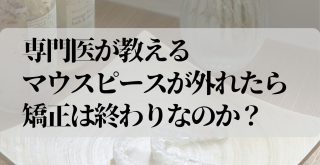歯科矯正治療を考えているけれど、「費用が高額で迷っている」「医療費控除が使えるのかわからない」とお悩みではありませんか?
実は、多くの方が「すべての矯正治療が医療費控除の対象になる」と思い込んでいたり、逆に「対象にならない」と諦めていたりします。
実は治療費だけでなく通院の交通費も対象になる点や、過去5年分まで遡って申請できる点など、知っておくと大きなメリットがある情報があります。
この記事では、歯科医師の立場から、医療費控除の仕組み、対象となる条件、手続き方法までを分かりやすく解説します。
歯並びの悩みを抱えたまま年を重ねていませんか?今からでも遅くありません。芦屋M&S歯科・矯正クリニックの経験豊富な専門医があなたに最適な治療法をご提案します。
クリックできる目次
芦屋M&S歯科・矯正クリニック理事長の松岡です。 芦屋M&S歯科・矯正クリニックは2003年に兵庫県芦屋市で開院しました。医師全員がインビザライン治療(マウスピース治療)・小児矯正・咬合誘導で秀でています。 インビザライン治療では1年間の症例数実績によって表彰される「プラチナステータス」に公式認定されています。 このブログで、インビザラインを始めとするマウスピース矯正、ワイヤー矯正など歯並びに関するさまざまな疑問にお答えします。もし、このブログで分かりにくい点がありましたら、お気軽にお問合せください。
【重要】歯科矯正は医療費控除の対象?ケース別解説

すべての歯科矯正が一律に医療費控除の対象になるわけではありません。ここでは、ケース別に詳しく解説していきましょう。
子供の歯科矯正で成長をサポートする治療は対象に
お子さんの歯科矯正治療は、ほとんどの場合、医療費控除の対象となります。
なぜなら、子供の歯科矯正は単に見た目を良くするためだけでなく、顎の発育や永久歯への交換といった成長過程をサポートする重要な医療行為だからです。
成長途中のお子さんは、歯並びやかみ合わせの悪さ(不正咬合)を放置すると顎の成長が妨げられ、将来的に咀嚼機能や発音に問題が生じる可能性があります。
このような機能的な問題を予防・改善するために行う矯正治療は医学的に必要性が高いと認められ、ほぼ間違いなく医療費控除の対象となるのです。
ご心配な点があれば、いつでも歯科医師に相談してください。お子さんの状態を詳しく診査し、治療の必要性と医療費控除の可能性について、具体的にアドバイスさせていただきます。
大人の歯科矯正の分かれ道!「治療目的」の証明
大人の歯科矯正が医療費控除の対象になるかどうかは、「審美目的」なのか「治療目的」なのかによって大きく異なります。ここが多くの患者さんが悩むポイントです。
基本的に、大人の矯正治療が医療費控除の対象となるのは、純粋な「見た目を良くしたい」という審美目的ではなく、機能的な問題を改善するための「治療目的」である場合です。
以下のような機能的問題があれば、「治療目的」と判断されやすく、医療費控除の対象となる可能性が高まります。
一見、「見た目をきれいにしたい」という動機で矯正治療を考えた場合でも、実際には機能的な問題が隠れていることが少なくありません。
たとえば、出っ歯や受け口などの不正咬合は見た目の問題だけでなく、噛み合わせの機能にも影響しています。
歯科医師の診断が決め手になります。自分では「見た目だけの問題」と思っていても、専門医の診察で「治療が必要な機能的問題がある」と診断されれば、医療費控除の対象となる可能性が高くなります。
そのため、矯正治療を検討されている方は、まず歯科医院でしっかりと診査・診断を受けることをお勧めします。
医療費控除の仕組み:誰が、いくら控除されるの?
医療費控除は、その年に支払った医療費が一定額を超えた場合に、税金の負担を軽減してくれる制度です。
医療費控除の計算式は次のとおりです。
その年に支払った医療費の総額 - 保険金などで補填される金額 - 10万円(または総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額等の5%のいずれか低い方)
例えば、年間の医療費が50万円で、保険金などの補填がない場合、50万円から10万円を引いた40万円が控除額となります。この金額があなたの課税所得から差し引かれ、結果的に税金が軽減されるのです。
医療費控除には以下のポイントがあります。
- 医療費が10万円(または所得の5%)を超えていないと、控除を受けることができません。
- 納税者本人だけでなく、「生計を一にする家族」(配偶者、子供、親など同居家族)の医療費もまとめて申告できます。
医療費控除は「所得控除」の一種であり、支払った医療費がそのまま還付されるわけではありません。課税所得が減ることで、結果的に税金(所得税・住民税)が軽減される仕組みです。例えば、所得税率が20%の方の場合、40万円の控除が認められると約8万円の税金が軽減されることになります。
医療費控除の対象となる費用・ならない費用

歯科矯正治療に関連する費用のうち、どの費用が医療費控除の対象となり、どの費用が対象外となるのか見ていきましょう。
控除に含められる費用
医療費控除の対象となる歯科矯正関連の費用には、以下のようなものがあります。
| 対象となる費用項目 | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 直接的な治療関連費用 |
|
|
| 医薬品代 |
|
一般的な歯磨き粉や洗口液など、日常的な口腔ケア用品は対象外 |
| 通院のための交通費 |
|
領収書や交通費の記録(利用日、経路、運賃など)を必ず保管しておきましょう |
控除に含められない費用
残念ながら、以下の費用は医療費控除の対象とはなりません。
- 純粋な審美目的の処置:機能的治療と同時に行う場合でも、審美目的の処置は分けて考える必要
- 治療に直接関連しない物品:歯科医院で購入した歯ブラシ、歯磨き粉、洗口液など
- 自家用車での通院経費:自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代
- デンタルローンや分割払いの金利・手数料
- 一般的な治療費を著しく超える高額な材料費
特に注意が必要なのは、デンタルローンの金利と自家用車の経費です。
多くの患者さんが矯正治療費の支払いにローンを利用したり、通院に自家用車を使用したりします。しかし、これらの関連費用が控除対象外であることを事前に理解しておくことで、適切な資金計画を立てることができます。
医療費控除の申請方法:ステップ・バイ・ステップ解説
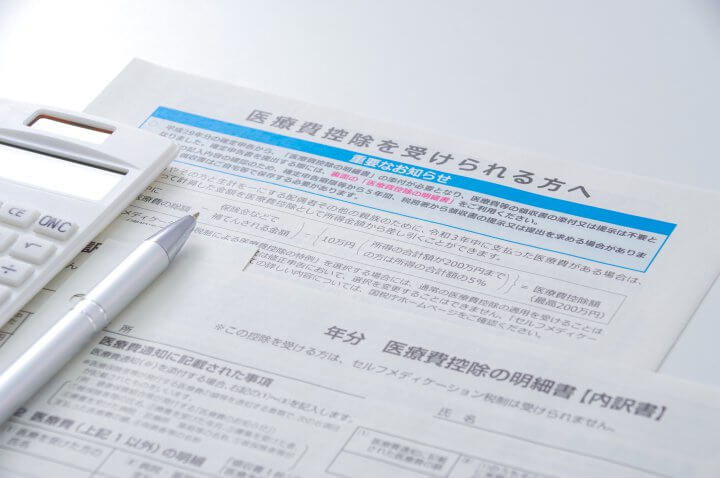
医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。ここでは、医療費控除を申請するための具体的な方法を分かりやすく解説します。
手続きのタイミングと場所:いつ、どこで?
医療費控除の申請は、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費について、翌年の確定申告期間中(通常2月16日から3月15日まで)に行います。
申告場所には以下の選択肢があります。
- 所轄の税務署の窓口に直接提出
- 郵送による提出
- 国税庁のウェブサイト「e-Tax(電子申告)」を利用したオンライン申告
忙しい方には、e-Taxを利用したオンライン申告がおすすめです。自宅からインターネットを通じて24時間申告が可能で、書類の郵送や窓口での待ち時間が不要になります。
必要書類リスト:これだけは揃えよう
医療費控除の申請には、以下の書類が必要です。
- 確定申告書(A様式またはB様式)
- 医療費控除の明細書(国税庁のウェブサイトからダウンロード可能)
- 源泉徴収票(給与所得者の場合、勤務先から発行されるもの)
- マイナンバー(個人番号)が確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)および本人確認
- 書類
- 還付金を受け取るための振込先口座情報
保管・提示を求められた場合に提出する書類(原則5年間保管義務あり)として以下が挙げられます。
- 医療費の領収書(歯科矯正費用、薬代など全て)
- 通院にかかった交通費の記録(日付、利用区間、運賃などを記載したメモや、交通系ICカードの利用履歴など)
- デンタルローンを利用した場合の契約書の写しや支払明細書
以前は医療費の領収書を全て提出する必要がありましたが、現在は「医療費控除の明細書」を作成・提出し、領収書は自宅で5年間保管するというルールに変わっています。
書類は多いように感じるかもしれませんが、一つずつ確認していけば問題ありません。特に領収書と交通費の記録は、日頃からきちんと整理しておくと、申告時の手間が大幅に軽減されます。
支払い方法と控除のタイミング:ローンや分割払いは?
歯科矯正費用の支払い方法によって、医療費控除を申請できるタイミングが異なります。まず、基本原則として医療費は、実際にその費用を支払った年の医療費控除の対象となります。
クレジットカードで支払った場合、その治療費はカード利用日(実際にカードを切った日)の属する年に控除対象となります。カードの引き落とし日ではない点に注意が必要です。
デンタルローンを利用して治療費を支払った場合、治療費の総額(ローンの元金部分)はローン契約が成立した年(ローンを組んだ年)に全額医療費控除の対象となります。ローンの返済期間にわたって分割して控除するわけではありません。
歯科医院との契約に基づき、治療費を分割で支払っている場合は、その年に実際に支払った金額が、その年の医療費控除の対象となります。
歯科矯正と医療費控除Q&A

歯科矯正治療と医療費控除に関して、患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。
Q1: 治療の途中でやめた場合も対象になりますか?
はい、対象になります。治療を途中で中止した場合でも、その年(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費が10万円(または総所得金額等の5%)を超えていれば、その超えた部分について医療費控除の対象となります。
治療の継続が難しくなった場合でも、それまでに支払った費用については控除の対象になりますのでご安心ください。
Q2: 家族の分もまとめて申請できますか?
はい、できます。納税者本人と生計を一にしている配偶者やその他の親族(子供など)のために支払った医療費は、納税者本人の医療費と合算して申告することができます。
「生計を一にする」とは、共通の資金で生活を営んでいる状態を指します。たとえ別居していても、生活費を送金しているなど生計を共にしていると認められる場合は対象となります。
Q3: 診断書は絶対にもらっておくべきですか?
確定申告の際に診断書の提出は必須ではありません。しかし、特に大人の歯科矯正の場合、税務署が治療目的の確認のために診断書の提出を求めることがあります。
提出を求められた際に用意できないと、控除が認められない可能性も否定できません。
そのため、必須ではないものの、特に「治療目的」であることを明確にしたい場合や、税務署からの問い合わせにスムーズに対応するためには、事前に歯科医師に相談し、診断書(または治療計画書など、治療の医学的必要性がわかる書類)を発行してもらい、保管しておくことをお勧めします。
診断書は通常、費用が発生しおよそ3,000円〜5,000円ほどです。なお、この診断書にかかる費用は医療費控除の対象とはなりません。
Q4: 医療費控除の申請を忘れていました。もうダメですか?
いいえ、諦めるのはまだ早いです。医療費控除は、過去5年間まで遡って申告(還付申告)することができます。
もし過去の歯科矯正費用やその他の医療費について申請し忘れていたものがあれば、今からでも手続きが可能です。ただし、各年ごとに申告が必要で、その年の領収書や記録が必要になります。
まとめ
歯科矯正治療の医療費控除について、詳しく解説してきました。お子さんの矯正はほぼ確実に控除対象になりますが、大人の場合は「治療目的」か「審美目的」かが判断基準となります。
医療費控除を利用するには、年間の医療費が10万円を超えることが条件ですが、家族全員の医療費をまとめることもできます。
治療関連費用だけでなく、通院交通費も控除の対象になる点もぜひ覚えておきましょう。
申請は翌年の確定申告時に行いますが、過去5年分まで遡って申請可能なので、以前の治療分も諦めないでください。
芦屋M&S歯科・矯正クリニックでは治療内容の説明はもちろん、医療費控除に関するアドバイスも行っています。歯並びのお悩みとともに、経済的な不安も、ぜひ専門家に相談してみてください。
よくある質問
歯科矯正のためのデンタルローンを組みました。医療費控除はどの時点で受けられますか?
デンタルローンを利用した場合、ローン契約を結んだ年(ローンを組んだ年)に、治療費の総額(ローンの元金部分)が一括で医療費控除の対象となります。
例えば、2025年に100万円のローンを組んだ場合、返済期間が5年間であっても、100万円全額が2025年分の医療費控除の対象となります。
歯科矯正のための通院交通費は医療費控除の対象になりますか?
はい、公共交通機関(電車・バス・タクシーなど)を利用した場合の通院交通費は医療費控除の対象となります。自家用車のガソリン代や駐車場代は残念ながら対象外です。
お子さんの治療に親が付き添う場合、親の交通費も対象になります。交通費の記録(日付、経路、運賃など)を必ず残しておきましょう。
歯科矯正は高額なので月々の分割払いを考えていますが、医療費控除はどうなりますか?
医療費は実際に支払った年の医療費控除の対象となります。支払い方法によって控除のタイミングが異なります。
- クレジットカード払い:カードを使用した日の属する年が対象(引き落とし日ではない)
- デンタルローン:ローンを組んだ年に元金全額が対象
- 医院への直接分割払い:各年に実際に支払った金額がその年の対象
分割払いの場合は、毎年の支払額に応じて複数年にわたって医療費控除を受けることになります。ただし、各年の医療費が10万円の基準を超えるかどうかが重要なポイントです。